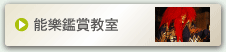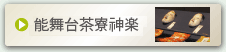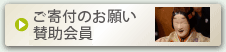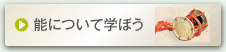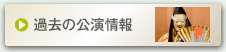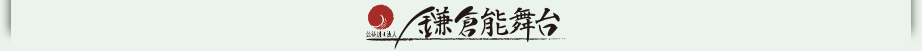能の雑学

|
1. チケットの手に入れ方 |
|
能のチケットの手に入れ方がわからない、という電話を頂くことがあります。 ただ、演目によっては、とってもヘビ-でマイナ-な曲だったり、とても長い長い通ムキの番組構成だったりすることもあるので、初めて能を見てみよう、という方は、チケットを購入する前に、その窓口で初心者向けの公演かどうか確認 なさったほうが無難だと思います。 |
| 2. 能舞台から出たことわざ |
|
「板につく」 能役者が舞台の上を吸い付くような足もとで歩くことから転じて、職業・任務などがその人にぴったり合うという意味。 「檜舞台を踏む」 歌舞伎役者が、あこがれの能舞台を踏んだらどんなに嬉しいだろうと思う気持ちからでたらしい。転じて、自分の腕前を披露する晴れの機会を得るという意味。 |
| 3. 「宗家」 |
|
もともと能の世界では「家元」とは言わず「宗家」と呼びます。 これは疑似天皇大家族制を取り入れたもので、その多くは世襲制で、嫡男は生まれながらに宗家になる星の下に生まれたという事になります。 しかし現在の能楽界の宗家の中で血筋を絶やさず続いてきたのは、シテ方観世流、小鼓方大倉流、太鼓方観世流だけになっています。 万が一血筋が絶えた場合はその流儀の代表者が「宗家預かり」となって流儀を運営していき、何代か後に宗家となっています。 宗家の持つ代表権とは「玄人の認定」、「免状の発行権」、「謡本の著作権」等で、その一部はその下の職分家に任されています。 現在のルールでは宗家を継承する際にその流儀の全玄人の署名・捺印が必要と言われ、結構手間の掛かる手続きが必要となっており、トラブルの原因にもなっています。 しかし現在の宗家の方々はそれぞれの流儀を上手くまとめ上げ、能楽界の隆盛を築き上げて来たことは事実であり、この封建的な制度を上手く利用しているのも事実です。 |
| 4. 舞台の下の瓶 |
|
「舞台の下には足拍子の音を良くするために瓶が埋まっているって本当ですか?」と質問がありました。 いまは、本来は音を響かせるのではなく、不快な振動数の音を消すためだと言う説が有力になっています。 舞台によって埋めてある物と木枠を組んで据え置かれている物があって、その置き方は最初に舞台の持ち主が拍子の音を正面の客席で聞きながら調整していたそうで、極めて感覚的な物と言えます。 足拍子はただ力を入れて舞台を蹴ればいいと言う物ではなく、うまく踵で踏まないとキレのある大きな音が出ません。舞台によっても音は色々ですが、あまり舞台を堅く締めすぎると足が痛いばっかりで全然音のでない舞台になってしまいます。 拍子の踏み分けは、男性の役の時は足をモモが水平になるくらいまで上げて(当然足は前に出ます)強めに踏み、女性の役は足を垂直に少し上げて、なるべく前に出ないようにするのがコツです。 音を出さない足拍子を「抜き足」や「けもの足」と言う人もいます。これは「鷺」や「猩々」等にあり、独特の型として扱われます。 また、曲の最後にシテが右に向いて踏む二つの拍子を「留拍子(とめびょうし)」と言います。曲によっては踏まずに二足ツメ足をして終わる場合もありますが、これは静かな曲か、シテが馬や車のような乗り物に乗って立ち去っていく時の演出です。 自分がシテを舞っていて、「この曲は留拍子だったっけ?ツメ足だったっけ??」と迷ったりすることもあります。 |
| 5. 見台(けんだい) |
|
見本(けんぽん)で謡う時に(暗記しないで、本を見ながら謡うことです)、謡本を載せる譜面台の役割をする木の箱の事を、「見台」と言います。 横に、流儀によっていろいろ違う模様が透かし彫りに彫ってあり、たいてい左右対称ですが、観世流のは、左に月、右に瓢箪と決まっています。 これは観世流中興の祖、観世黒雪の辞世の歌、「わが宿は 菊を籬(まがき)に露敷きて 月にうたふる瓢箪の声」に因んだ物で、この和歌が観世流の謡曲の秘伝を現した庭訓と言われ、忘れぬよう、見台に刻みつけたものと言われています。 すなわち、わが宿とは家芸のこと。菊の籬のように美しく霜にも強く、露のように潤いを持ち、瓢箪のように腹をふくらませ、口を締めて八分目に謡え(月は八分月)、という事らしいです。 よろしかったら、見台の写真をどうぞ。こちら(別窓) |
| ↑に戻る |
| 6. 舞台の小道具「笹」 |
|
Q>日舞で、狂乱もので笹の葉を持つのは、お能から来ていたのですね。でもなぜ笹なのでしょう? A> 「笹」については色々な説がありますが、百人一首に 「このたびは幣もとりあえず手向山紅葉の錦神のまにまに」と言う和歌があります。これは昔は御幣がないときに山の木々や笹を代わりにしたと言う風習があった事を表しているのだそうです。 能の狂女というのは元々神が憑いて舞い狂う巫女のことなので 御幣ばかりでは代わり映えがしないので笹に白布や茅の輪を附けて持たせたのが 狂女笹のいわれではないかと言うのが有力な説のようです。 巫女というのは神に仕える芸人でもあり、女性が子供や恋人を訪ねるために旅をするには 狂女と言う名の旅芸人に身を落とさなければ叶わなかったので その名残として御幣の代わりに笹を持ったのではないでしょうか。 |
| 7. 舞台の小道具「杖」 |
|
Q>能の中で怨霊や鬼がつえを持って出てくるのはなぜですか? あのつえには、どういう意味があるのでしょうか? A> 能には色々な種類の杖があります。 龍神や般若の面を使った役の時にもつのが「打杖(うちづえ)」で これは山々の木を折って武器にした物を小道具として作った物のようです。扇よりは大きいので見栄えがいいというのも理由の一つでしょう。 色に赤・紺・萌黄があり、赤は「葵上」などの女性の鬼の役に、紺は龍神や「殺生石」の狐など。萌黄は「安達原」などの紅無(いろなし)の装束の時に使っています。 怨霊系の「藤戸」「善知鳥(うとう)」などの杖は「幽霊杖」と言って他の老人などの使う物と同じ物です。 しかし杖の付き方・使い方に色々な違いがあり、老女・老人等とはずいぶん雰囲気が違うものです。 この他にも「山姥」「恋重荷」等で使う「鹿背杖(かせづえ)や「弱法師」「蝉丸」などの「盲杖(めくらつえ)」などがあります。 |
| 8. 舞台正面の向き |
|
Q> 現在の能楽堂の多くは舞台正面が南に向くように建設されていると聞きました。しかし15世紀頃の能舞台は資料を見る限り北向きです。なぜ北向きではならなかったか。そして、時代を経て、なぜ北から南へ180度向きが変わったでしょうか。 A>現在の能楽堂の向きは特に決まってはいないようです。敷地の関係や設計の都合が優先されています。 昔の能舞台が北向きだったのは、昔から 「 貴人は南面す 」 と言う言葉があり、帝や将軍は必ず南を向いて座ることになっていたからだそうです。そのために舞台は必ず北向きにしなければなりませんでした。 また、当時は野外の舞台だったため時刻によって舞台照明が(日光が)変化することを嫌ったために、一番変化が少ない北向きにしたとも言われています。 |
| 9. 室内舞台の屋根 |
|
Q>能楽堂は本来屋外にあり、その名残で現在の室内能楽堂は屋根つきの舞台になっていると聞きました。能舞台が屋外から室内に移動する経緯がどうしてもつかめません。 A> 明治以前の能は、ごく少数のVIPのために演じられる演劇で、舞台は屋外にありました。それが明治維新以降は一般を対象とする物に変化せざるを得なくなり、それまでは白州だったところにも観客を入れるようになり、舞台の屋根のひさしが段々長くなって、最終的に建物の中へと入ったようです。 今の能舞台の屋根が二重になっているのは、真ん中の梁に道成寺の鐘をつり上げるための滑車を付けるために必要だからです。 |
| 10. 貴人口 |
|
Q> 「貴人口(きにんぐち)」 というものがありますが、現在でも使われることがあるのでしょうか。公演中、また公演以外に、もし使われるとしたら、どういう人、どういうことで使用されるのでしょうか。 A> 現在は全く使われておりません。昔は秀吉のように偏屈な大名が「頭を下げて舞台に出入りをするのは嫌じゃ」等と言ったために、大きな扉を付けたのだそうです。 |
| ↑に戻る |
| 11. 橋掛かり |
|
Q>「橋懸かり」が昔は左右両態にあったと聞きました。また舞台後ろ、南北に、橋懸かりをつけるものが典型的なものであるという意見もあり、こちらでは情報が錯乱しています。いったい橋懸かりはどのように発展していったのでしょうか。また、形の類似ということで、歌舞伎の花道と同じ由来のもだと考えるのは少し乱暴でしょうか。 A>橋懸かりは、一番最初の頃は舞台の両端に真後ろに付いていたそうです。 それが桃山時代の「障壁画」の影響で、後ろに鏡板を置いて松の絵を書くようになったため、両横に付けて、そのうちに下手側のみを演技で使用するようになったそうです。 歌舞伎は舞台が「額縁形式」の為に、花道を前方に付けていますが、能の橋懸かりは遠近感を強調するために後退角を付け、松も手前側から次第に小さくする工夫がなされています。 歌舞伎のように役者がお客様にお尻を向けて登場することは、観客層の違いから絶対にあり得ないことだと思います。 |
| 12. 能の小書き |
|
能はひとつの演目でもその解釈はいろいろにあり、演じる人、面、装束、囃子、さらに小書(特殊演出)によって、まるで違う印象の曲目となります。 例えば「船弁慶(ふなべんけい)」で、後シテ知盛が普段は荒武者として演ずるのに、「前後之替(ぜんごのかえ)」の小書がつくと公達となり、狩衣に真の太刀という品のある扮装で、動きも優雅になります。「田村」の「替装束(かえしょうぞく)」は、面が平太(へいた)から天神に、法被が狩衣に、烏帽子が唐冠(とうかんむり)に、太刀が背中に背負った剣に変わり、日本的武将から、帰化人の征夷大将軍へと変身します。 また、囃子ごとによる変化も小書になります。 「葵上」や「砧(きぬた)」の「梓之出(あずさので)」は、普通一声の囃子で出るシテが、鼓の「梓」の手に乗って出るということですし、「窕(くつろぎ)」は、舞いの途中で囃子の手が変わり、シテが橋掛かりに行ってしばらく囃子を聞いてから舞台に戻って残りを舞い続けるという趣向で、「融(とおる)」「海士(あま)」「玄象(げんじょう)」なあど早舞物(はやまいもの)にやりますが、同功のものが「安宅(あたか)」の「滝流(たきながし)」、「天鼓(てんこ)」の「弄鼓之舞(ろうこのまい)」など、数多く見られます。 |
| 13. 能の小書き2 |
|
Q>小書とは何ですか?また、なんのためにあるのですか? A>小書きとは、能の特殊演出のことです。 まず「橋弁慶」の「笛之巻」。これは元々橋弁慶の前シテの部分だったそうですが、 あまり面白くないので半能として後シテだけを演じていたものに、 別の前シテを新たに作ってつけたのが現行曲と言われています。 廃曲にするのはもったいなかったので小書として残したようです。観世流ではこのように前シテを廃止してしまった曲が結構あります。 「菊慈童」「岩船」「金札」などがそれにあたります。( 他の流儀ではきちんと前シテがあります。) 他には動きを少なくしたり、途中の謡をゆっくりにする演出のもの。 「前後之替(ぜんごのかえ・船弁慶)」 「白頭(しろがしら・小鍛治など)」 などですが、これは体が利かなくなった老人や、不器用なお殿様が謡に遅れたりしないために考えられたもののようです。 いかにも難しそうに見えて、格好の良い型で、 しかもやってみると謡がゆっくりな分余裕を持って演じられる。 とてもよく考えられた演出です。 その他、番組立ての都合で同じ舞が重なったり 「語(かたり)」と言う謡の曲が続いたときなどに使われる小書もあります。 大原御幸(おはらごこう)の「寂光院(じゃっこういん)」の小書などがそれにあたります。(見たことも聞いたこともありませんが・・・。) 舞の長さを替える物も多くあります。 「クツロギ」「舞返(まいがえし)」「弄鼓之楽(ろうこのがく)」等です。 やはり昔から人気のあった曲にはいろんな小書が考えられたようです。 熊野(ゆや)・融(とおる)等が良い例ですね。 観世流にはものすごく小書がありますが宝生流さんは殆ど小書がありません。そのため小書きは物凄く難しく、扱いの重い扱いで、滅多に上演されません。観世の場合は「重キ」と「素」の付く小書が扱いが重く、昔は宗家限りの「一子相伝」だったそうです。「重キ黒頭」「素囃子(しらはやし)」などがそうです。 |
| 14. 能装束 |
|
Q> 能の衣装というのは、1曲ごとに全く違う物を用意するのですか? A> 一曲毎ではありませんが、同じような曲目の中でも幾つかのパターンがありまして、それぞれ違う装束が必要になります。今回のメルマガにあった老人でも「着流し」「大口・無地熨斗目」「大口・小格子厚板」 等がありますし、それぞれに色目も何パターンか無いと具合が悪いです。 すべての曲を一応上演できるだけの装束を揃えるには、膨大な費用と時間が掛かります。 Q> 個人で用意すると莫大な量になると思うのですが、家元が一括管理して公演の時に演者さんが借りる感じになるのでしょうか? A> 私のところでも独立した装束蔵を持っております。観世宗家やそれに準じた家では普通の一軒家相当の広さの蔵が必要になります。ただ、普通の能楽師は自分で装束は持ちません。すべて師匠家から拝借するのが 普通です。 Q> TVで京都の狂言茂山家のドキュメンタリーを見た時に戦前からの衣装を管理している・・・ような事を紹介していました。やはり古い衣装の方が良いものなのでしょうか? A> もちろん古い装束は良い物(金に糸目を掛けずに作られた物)が多く、魅力はありますが 一枚だけ持っていても意味がありません。着ている一式全部が時代の揃った物ならばさぞかし素晴らしい舞台映えのする装束だとは思いますが、なかなか見る機会はありません。 特に最近はみんな背が高く、古い物は寸法が合わなくなってきています。 |
| 15. 能装束2 |
|
Q> 衣装は大体の時代をあわせて使用するものなのですか?古い袴と最近作った狩衣なんて組合せはしない物ですか? A>時代を合わせられれば最高ですが、現実にはなかなかいかないものです。 古い装束には寸法が小さい物が多く、付け方によって使えたりダメだったりしますので、古い物と新しい物を組み合わせることもいたします。 痛み方も物によって違うので、すべての装束が同じようにヘタってくる物でもありません。 ただ「実盛」の錦の厚板が新品では全く似合いませんし、下の半切れがピカピカと言うのも違和感がすごくあります。 Q> 着物では「この着物は能に由来する文様なので格が高い」なんて言い方をよくします。そもそも能の衣装の文様はどこに由来するものなのでしょうか? A> 正倉院文様からも来ていますし、自然発生的に出来た物も多いようです。 特に自然の草花をそのまま衣装にデザインするのは日本人だけだそうで、能では「草花だけ」は庶民の衣装、「草花が、扇に描いてあったり花籠に入っている」のは高貴な女性の着る物と決まっています。 平家の揚羽の蝶や源氏の笹竜胆も旗印などから来た文様です。 逆に「黒船段」の柄などは、浦賀に黒船がやってきた嘉永年間頃にはやった柄なのでそういう名前が付いたそうです。このように、由来は様々で、はっきりとはわからないようです。 |
| ↑に戻る |
| 16. 舞台の上の決まり事 |
|
小道具の音 舞台の上でシテが杖や竿を下に置くときに、まだ使うときは音を立てぬよう静かに置き、これで不要になるため後見に引いて欲しい時は「パタッ」と音を立てて落とします。 これを守らないと、後見が引いてくれただろうと思いこみ、立って歩き出した途端、足でけっ飛ばすという醜態を晒すことになります。 後見は合図が決まっている以上、型として使わない事がわかっていても、勝手に判断をすることはできませんので、あくまでもシテの責任において決まり事は守らなければなりません。 |
| 17. 能の約束事 |
|
能には能の約束があって、それを理解していないと、舞台の上で行われていることがわからないことがあります。 例えば、場面設定は登場人物や地謡の言葉によって行われるとか、立ち方全員が後ろ向きになって改めて向き直った時は場面がかわるとか。 萩屋や藁屋とかの作り物に引き回し(布)がかかっている間は、舞台上にまだそれはないと考えるとか(例外もあります)。 また方角も、舞台の向きに関係なく、常座に立ってワキ座が東、目付柱が南、揚幕が西、切戸口が北と決まっています。 型付けには正確にその方角を向くように書いてあっても、やり勝手が良いように自己流に直すこともあります。 弱法師で「淡路絵島、須磨明石。紀の海までも」というところでズーッと南から西へカッコ良く見回したら、土地の人に「そっちには紀の海はおまへんで。四天王寺からは南だす」とやりこめられているのを聞いたことがあります。 |
| 18. 道成寺鐘入り |
|
長い能の歴史の間には、数多くの事故や失敗例もあります。 明治時代に、鐘の中にラムネを入れておいて、鐘入り後飲もうと栓を抜いたらポンと音が場内に響き、「また鐘が落ちた」と、どよめいたとか。 はさみや鬘を床に忘れるなんてことも、良くあります。 鐘を上げたら後ろ向きに座っていたなんていうのも実にしばしば聞く話です。 観世流は鐘の真下に入り、拍子を数踏んで飛ぶので一番安全です。宝生は鐘の下に入りますが、斜め後ろに向いて飛ぶそうです。喜多流も同じ向きですが、拍子の数が少ないだけ、鐘を下げるタイミングが難しいようです。 一番怖いのが金剛流で、鐘の外側から手を掛け、斜めに身をよじって鐘の中に飛び込むという最もスリリングな演技をします。 飛び上がるのと鐘が落ちるのが同時ですから、微妙なタイミングのズレによっては頭を強打したり(天井に布団はつけてありますが、70kgもある鐘が当たるのですから大変です)、縁に膝が当たって叩きつけられ膝の皿が割れたりという事故も聞いたことがあります。 鐘に入ったら後の面が割れてしまっていて、シテがとっさの機転で小指を噛んで、血で前シテの女面に隈取りを描き、その凄まじい後シテの顔に喝采を浴びた・・というのは多分作り話でしょう。 |
| 19.祝言謡 |
|
Q.おめでたい席で謡を披露するようですが、どんな謡がうたわれるのでしょうか? A.結婚式では、高砂(定番)・猩々・皇帝・鶴亀等、新築・落成記念では、猩々・菊慈童・養老(建造物は火を嫌うことから水に縁の曲を選ぶと教わりました)、入学・成人祝いでは、烏帽子折、等を謡います。 Q.結婚式での「高砂」はどこを謡うのですか? A.玄人の結婚式で謡われるのは「四海波」と言う部分です。地謡の初同「四海波静にて~君の恵みぞありがたき」迄です。 「高砂や~」の待謡は有名ですが、ここからですと一番最後の「千秋楽は民を撫で万歳楽には命を延ぶ相生の松風颯々の声ぞ楽しむ」迄謡わないと祝言になりません。 |
| 20. 謡初の式(うたいぞめのしき) |
|
江戸時代、毎年正月二日に江戸城本丸において「謡初の式」が吉例として行われていました。観世太夫による「四海波」の独吟、「老松」「東北」「高砂」の居囃子三番の演奏がされました。 この謡初が終わるまで江戸市中は音曲停止のふれが出され、式の終了を知らせる太鼓の音が江戸城から聞こえると始めて芝居小屋の幕が明いたものだそうで、江戸っ子には馴染み深い行事だったようです。 この行事は全国の大名諸侯が将軍からの堅めの盃を頂く間のBGMとして謡われていたもので、最後に列席の大名が裃の肩衣を脱いでお気に入りの能役者に投げ与える習慣がありました。 能役者はその肩衣を拾い集め、付いている紋から誰の物かを判断して大名の家に後日お届けに上がると、大名の禄高に応じたご祝儀を頂けたそうです。 |
| ↑に戻る |
| 21.能楽師のなり方 |
|
「どうして能楽師になったのですか?」「どうやったら能楽師になるんですか?」と言う質問が学生能などでも良く出ます。「能楽師」「狂言師」という職業があるということに気付き、この人たちはどうしてこの職業に就いたのだろうと興味を持っていただけることは、能楽に興味を持ってもらう第一歩だと嬉しく思います。 玄人になるための修行課程を、観世流シテ方を例としてお話しましょう。 まず玄人というのは宗家から認証され免状を交付された者を指します。その中にもいくつかの階級があって「分家(観世鉄之丞家)」「職分家(観世喜之家・片山家・梅若家など」「準職分家(その他多くの家)」「師範」となっています。 宗家・分家は世襲制となっており、それ以下の家は宗家が主催する「研修会」に最低5年間出席して玄人となります。実際に玄人を養成できるのは「職分家」以上の家に限られており、準職分家の子弟は職分家に内弟子(現在は研修生と言います)に入って修行を積み、宗家への推薦を貰って独立します。 職分家の子弟(多くは長男)は宗家・分家に入る人もいますし父親の元で修行をする人もいますが、いきなりは職分にはなれず、準職分を経て40歳を過ぎてから再度職分審査会の推薦により職分として認められます。 「師範」は内弟子に入る必要はありませんが、玄人として最低限の楽屋でのマナーは必要ですので、定期能などに出勤して楽屋内での立ち居振る舞いを学んだ後に師匠家の推薦を取ります。 この他に「名誉師範」と言うものもありますが、これはあくまでもアマチュアとしての称号で、将棋や囲碁の「アマ○段」の最高位みたいなものだと考えて下さい。 玄人の子供はそれこそ立って歩けるようになったときから稽古が始まります。大体2歳半から3歳くらいでしょうか。始めはホンのお遊びとしてですが、お扇子を持って、舞台に慣れさせるための訓練は小さいうちから始まるのです。 初舞台は仕舞が多く、ヨチヨチと「よわいをしゃじゅくりゅ~」と舞う姿はとても可愛いものです。4~5歳で能の子方が付くようになり、たいてい子方の初舞台は「鞍馬天狗」の「花見」が一般的で、かわいいお子さんが大勢ゾロゾロと舞台を歩くだけで十分華やかに見えるものです。この後「鞍馬天狗(牛若)」「安宅」「望月」などの子方を勤めてエリートコースを進む子供は「鷺」のシテを少年時代に勤めます。そして牛若が曲中で元服をする「烏帽子折」の子方を最後とするのが最高の終わりかたになります。 この後は声変わりや勉強があるために舞台にはしばらく出せなくなります。世阿弥も花伝書「時分の花」という段に書いているとおり、見た目は大人でも技術的には全く出来上がっていないので、ここで基本的な稽古からやり直して今度は玄人として再デビューする日を待つ事になります。中学・高校の6年間に囃子の稽古や装束付け、楽屋での気配りなどを徹底的に叩き込まれてから内弟子になり、師匠家に最後の仕上げをして貰って独立するわけです。 趣味から入って大学くらいから始めて玄人になるという道もあります。「親の跡継ぎだから」と言う理由でこの仕事をしている人の何倍もの情熱を持ってこの世界に入ってきた勇敢な人たちです。 とにかく、観世流のシテ方の場合「師匠家に5年間住み込みの内弟子修行(書生)をする」という今時の若い人には信じられないハードルがあります。 囃子方やワキ方、狂言方には、国立能楽堂の養成科という入り口もありますが、最終的に玄人として役に立つ人間になるには、さらなる努力と才能と運と協調性(?)が必要です。 |